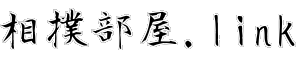相撲用語辞典【ら・わ】
2015/1/3
- 力士会[りきしかい]
力士生活の向上のため力士の立場から協会へ提言することを目的にした会であり、十両以上の力士で構成している親睦組織
引退相撲が行われる際は、力士会は無償で協力することとなっている。
またかつては力士会主催で「力士大運動会」も行われていた。
- 連合稽古[れんごうけいこ]
一門内の部屋が合同で行う稽古のこと。
- 若い者[わかいもの]
幕下以下の力士の別称。
- 若者頭[わかいものがしら] (詳細)
幕下以下の力士の監督、稽古の指導をする人。また、本場所の取組の進行係や雑用(所属部屋での雑用も含め)もこなす。
世話人同様元力士から選抜され、現役時代の最高位の四股名を名乗る。
また、NHKのBS放送では幕下の取組の解説も務める。(現在の若者頭は前進山以外全員が担当。)
定員は8名で、現在は全員が最高位十両以上。
- 脇が甘い[わきがあまい]
相手にすぐ差し込まれてしまうこと
- 脇が堅い[わきがかたい]
肘を脇腹につけて相手の差し手を防ぐこと
- 割り[わり]
取組のこと。優勝決定戦は「割り」とは言わない。
- 割紙[わりがみ]
取組を書いた紙のこと。幕内、十両だけのものは「小割」「顔ぶれ」とも呼ぶ。